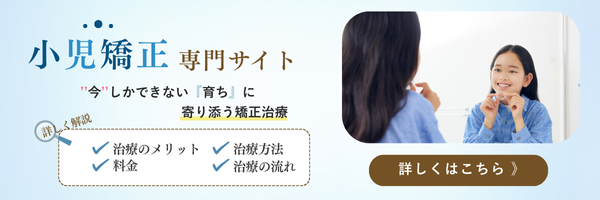赤ちゃんの歯医者デビューはいつから?0歳で受診するメリットと注意点を解説
2025年12月23日
▼目次
赤ちゃんの歯は生後6か月頃から少しずつ生え始めるとされていますが、どのタイミングで歯医者を受診すべきか迷う保護者の方は多いのではないでしょうか。早い時期から歯医者で口腔内の状態を確認してもらうことで、むし歯リスクに気づきやすくなります。一方で、「0歳で受診してもいいの?」「どんなことをするの?」と不安に感じることもあるかもしれません。今回は、赤ちゃんが歯医者に通い始める時期の考え方や、0歳から受診する目的について、恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科が解説します。
1. 0歳の赤ちゃんはいつから歯医者を受診できる?
赤ちゃんは0歳からでも歯医者を受診することが可能とされています。実際、多くの小児歯科では「歯が生え始めたら、または1歳になるまでに初めての受診を」と案内しているところが多く、むし歯予防や口腔内の発達を見守るうえで、早めの受診が望ましいと考えられています。
①歯が生え始めるタイミングでの受診が理想
一般的に、乳歯は生後6か月頃から生え始めるとされています。最初の歯が見えてきたら、口腔ケアのスタートラインです。この時期に歯医者を受診しておくと、正しいケア方法を教えてもらえたり、むし歯予防の準備がしやすくなることがあります。
➁歯の状態だけでなく、舌や歯ぐきの観察も重要
初回の受診では、歯だけでなく、舌の動きや歯ぐきの状態、哺乳のクセなど、口腔内全体の発育状況を確認することがあります。また、口腔内の健やかな成長を支えるためのアドバイスを受けられることもあります。
➂定期検診としての役割
0歳から定期的に歯医者に通うことで、むし歯や噛み合わせの異常を早期に発見しやすくなります。継続的なフォローを受けることで、将来的なトラブルに早く気づける可能性があります。
0歳での受診は「治療」ではなく「予防」と「確認」が主な目的といえます。赤ちゃんの健やかな口腔内環境をつくる第一歩として、早めの受診を検討しましょう。
2. 0歳で歯医者デビューをするメリットと受診の目的
赤ちゃんの時期に歯医者へ行くことは、将来的なお口の健康を守ることにつながります。むし歯の予防だけでなく、生活習慣や食事、発育に関するアドバイスも受けられる貴重な機会です。
①むし歯予防の知識を早めに得やすい
0歳での受診では、保護者向けにむし歯の原因や予防方法について、丁寧に説明してもらえることがあります。特に乳歯は歯の表面のエナメル質が薄く、むし歯になりやすいため、生え始めからのケアが重要といわれています。
②仕上げ磨きの方法を学べることがある
赤ちゃんの口腔内はとても小さく、仕上げ磨きに苦戦する保護者の方も多いでしょう。歯医者では、年齢や歯の本数に応じた磨き方のアドバイスを受けられることがあります。
➂噛み合わせや舌の使い方を診てもらえることも
歯の生え方だけでなく、舌の動きや顎の発育も確認されることがあります。おしゃぶりや指しゃぶりの影響、将来的な歯並びへの影響についても、早期にアドバイスを受けやすいのが特徴です。
④今後の通院がスムーズになりやすい
赤ちゃんのうちから通っておくことで、歯医者の雰囲気に慣れやすくなります。これにより、将来むし歯治療が必要になったときも、怖がらずに通える可能性があります。
早い時期から歯医者に慣れておくことで、赤ちゃんの口腔内の成長を見守りやすくなります。また、保護者にとっても、日々のケアを進めやすくなるきっかけにつながるでしょう。
3. 赤ちゃんの生え始めの歯を守るために知っておきたいポイントと注意点
赤ちゃんの乳歯は、大人の歯に比べてやわらかく、むし歯になりやすい特徴があります。そのため、生え始めからのケアがとても重要です。毎日のちょっとした習慣が、赤ちゃんの歯を守る力となるでしょう。
①歯が生え始めたらすぐにケア開始
歯が1本でも顔を出したら、清潔なガーゼや歯ブラシを使ってお手入れを始めましょう。最初はガーゼで優しくぬぐうだけでも十分といわれています。歯が増えてきたら、年齢に合った柔らかい歯ブラシを使い、仕上げ磨きを習慣化しましょう。
➁おやつと飲み物の選び方に注意
甘いおやつやジュースは、むし歯の原因になることがあります。赤ちゃん用のスナックでも砂糖が含まれているものが多いため、選ぶ際は成分表示を確認しましょう。飲み物は基本的に白湯かお茶がおすすめです。
➂哺乳瓶の使い方と就寝時の授乳に注意
哺乳瓶を長時間くわえさせたり、寝かしつけで授乳を続けると、口腔内に糖分がとどまりやすくなり、むし歯のリスクが高まることがあります。1歳を過ぎたら、コップやストローへの移行も検討しましょう。
④保護者の口腔ケアも大切
むし歯菌は、身近な大人の唾液を通じて赤ちゃんに移ることがあります。スプーンの共有やキスなども感染経路となり得るため、大人も定期的に歯医者に通い、口腔内を清潔に保つことが大切です。
赤ちゃんの歯を守るためには、家庭でのケアと生活習慣の見直しが欠かせません。小さな習慣の積み重ねが、むし歯のない健康な口腔内を育てる助けになるでしょう。
4. 恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科

恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、小児歯科において「怖い」「痛い」といった従来の歯医者のイメージを変えるための取り組みを行っています。お子さんが安心して通えるよう、治療前の雰囲気づくりや歯列矯正の早期対応、むし歯予防の栄養指導、さらには急な歯のトラブルやマタニティ歯科まで幅広く対応し、親子で通える歯医者を目指しています。
【恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科の特徴】
小児歯科のポイント①:歯医者に慣れる工夫
初めて来院するお子さんには治療を急がず、雰囲気に慣れる時間を大切にしています。スタッフとの会話やごほうびを通じて「歯医者は怖くない場所」という印象を持っていただけるよう心がけています。
小児歯科のポイント②:早期の歯列矯正に対応
子どもの歯列矯正は早めに始めることで、治療期間や費用を抑えることにつながります。当院では矯正歯科も併設しており、成長に合わせたご提案が可能です。
小児歯科のポイント③:予防のための栄養指導
虫歯は生活習慣や食生活とも密接に関係しています。歯磨き指導に加え、栄養面からのアドバイスも行い、日常的にむし歯予防をサポートしています。
小児歯科のポイント④:トラブル・マタニティ歯科にも対応
転倒による歯の怪我やマタニティ期の治療にも対応しています。妊娠中の方には無理のない体勢や薬の使用に配慮し、必要に応じて産婦人科とも連携しています。
恵比寿で小児歯科をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。親子で通いやすい歯医者として、お子さんの健やかな歯の成長をサポートいたします。初診や検診のご予約も随時承っております。
▼恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科について詳しくはこちら
https://www.ebisudc.com/kids/
まとめ
0歳から歯医者を受診することは、むし歯予防だけでなく、口腔内の正しい発育や生活習慣の見直しにも役立つことがあります。早い時期から口腔内の状態を確認することで、正しいケアの習慣づくりにつながるでしょう。生活習慣や授乳・おやつの工夫もあわせて意識しながら進めることが大切です。
0歳の歯医者受診についてお悩みの方は、恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科までお問い合わせください。
小児歯科に行く頻度はどれくらい?定期検診のタイミングと通院の工夫
2025年11月19日
▼目次
子どもの歯は成長とともに変化し、歯の状態や噛み合わせの状態も日々変わっていきます。そのため、小児歯科での定期的なチェックはとても重要です。しかし「どれくらいの頻度で通えば良いのか」「どんなことをしてもらえるのか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。小児歯科では、むし歯予防や歯磨き指導だけでなく、歯の生え変わりやあごの発育まで確認しています。今回は、小児歯科に通う適切な頻度と、定期検診のポイント、通いやすくするための工夫について恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科が解説します。
1. 小児歯科はどれくらいの頻度で行くのが良い?
小児歯科での通院頻度は、年齢やお口の状態によって異なりますが、基本的には3〜4か月に1回程度の受診が目安です。これは、むし歯の進行が早い子どもの口の中を定期的にチェックし、早期対応するためです。
①乳歯期の通院目安
乳歯が生え始める1歳前後から、3〜4か月ごとの定期検診を続けるのが理想です。この時期は生活習慣の影響を受けやすいため、早い段階からの通院で予防の習慣を身につけることが大切です。もちろんもっと早い時期から受診していただき、離乳食の始め方、身体の使い方などのお話もしています。毎月来院いただきながら少しずつ環境に慣れていただくようにしています。
➁幼児期(3〜6歳)の通院目安
自分で歯磨きを始める年齢ですが、磨き残しが多くなりがちです。歯医者でのフッ素塗布や歯磨きチェックを受けることで、むし歯の早期発見や予防につながります。
➂小学校低学年の通院目安
永久歯が生え始める時期です。歯並びや噛み合わせの確認も重要になります。3〜6か月ごとの検診で、歯の生え方やスペースを確認してもらいましょう。
④中高学年〜思春期の通院目安
部活や学校生活で不規則な生活になりがちな時期です。食生活の乱れや磨き残しが原因でむし歯が増える傾向にあります。半年に1回は通院し、定期的なケアを受けることが大切です。
⑤むし歯や治療後の再チェック
一度むし歯治療をした後は、再発防止のために3か月以内の再検診が勧められます。
定期的な通院を続けることで、むし歯の予防だけでなく、歯並びやあごの成長も確認できます。お子さんの成長段階に合わせて、歯医者と相談しながら通院間隔を決めていくとよいでしょう。
2. 小児歯科に行くとチェックしてもらえる内容
小児歯科の定期検診では、ただ「むし歯があるかどうか」だけでなく、成長に合わせた総合的なチェックが行われます。ここでは主な項目を紹介します。
①むし歯や歯ぐきの健康状態の確認
歯の表面だけでなく、歯と歯の間、歯ぐきの状態まで丁寧に確認します。初期むし歯が見つかれば、削らずにフッ素塗布などで経過観察ができる場合があります。
➁歯磨きの習慣と磨き残しのチェック
子どもの年齢に合わせた歯磨き方法の指導が行われます。染め出し液を使って磨き残しを可視化し、どこが磨きにくいのかを一緒に確認することが望ましいです。
➂フッ素塗布やシーラント処置
フッ素塗布は歯を強くし、むし歯予防に役立つとされています。また、奥歯の溝が深い部分にはシーラント(樹脂で溝を埋める処置)を行うことで、むし歯の発生を防げる可能性が期待されています。
④歯並び・噛み合わせの確認
永久歯が生え始める時期には、噛み合わせのズレや歯並びの乱れもチェックします。必要に応じて小児矯正の相談が行われることもあります。
⑤生活習慣や食習慣のアドバイス
甘いおやつの摂取回数、間食のタイミング、就寝前の歯磨き習慣など、日常生活の中で気をつけるポイントをアドバイスしてもらえることもあります。
定期検診は、むし歯予防だけでなく、子どもの「お口の成長」を支える大切な時間です。家庭と歯医者の連携によって、将来の歯の健康を守りましょう。
3. 小児歯科に通い続けるための工夫
小児歯科への通院を続けるためには、「子どもが怖がらない」「保護者が無理なく通える」環境づくりが大切です。通院が習慣化できると、将来的なむし歯予防にもつながります。
①歯医者への「怖い」イメージをなくす工夫
初めての通院では、診療台や器具に不安を感じる子もいます。まずは見学や簡単なチェックから始め、少しずつ慣れていきましょう。「歯医者=特別な場所」ではなく「定期的に行く場所」として慣れていくことが理想です。
➁親がリラックスして通院できる環境を選ぶ
保護者が緊張していると子どもに伝わります。キッズスペースやモニターがある、スタッフが子どもに慣れているなど、落ち着いた環境を持つ歯医者を選ぶことがポイントです。
➂通院を前向きな経験にする
治療後にごほうびを用意する、帰りに寄り道をするなど、通院を楽しい経験に変える工夫も大切です。
④通院日を生活リズムに組み込む
「季節の変わり目ごと」「長期休み前」など、通院を定期スケジュールに入れておくと継続しやすくなります。
⑤家庭で歯の話題を増やす
日常の中で「今日はきれいに磨けたね」「今度歯医者で見てもらおうね」といった会話を取り入れると、自然と意識が高まるでしょう。
小児歯科への通院は「治すため」ではなく「守るため」の習慣です。家庭と歯医者が協力し、子どもが前向きに通える環境を整えていきましょう。
4. 恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科

恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、小児歯科において「怖い」「痛い」といった従来の歯医者のイメージを変えるための取り組みを行っています。お子さんが安心して通えるよう、治療前の雰囲気づくりや歯列矯正の早期対応、むし歯予防の栄養指導、さらには急な歯のトラブルやマタニティ歯科まで幅広く対応し、親子で通える歯医者を目指しています。
【恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科の特徴】
小児歯科のポイント①:歯医者に慣れる工夫
初めて来院するお子さんには治療を急がず、雰囲気に慣れる時間を大切にしています。スタッフとの会話やごほうびを通じて「歯医者は怖くない場所」という印象を持っていただけるよう心がけています。
小児歯科のポイント②:早期の歯列矯正に対応
子どもの歯列矯正は早めに始めることで、治療期間や費用を抑えることにつながります。当院では矯正歯科も併設しており、成長に合わせたご提案が可能です。
小児歯科のポイント③:予防のための栄養指導
虫歯は生活習慣や食生活とも密接に関係しています。歯磨き指導に加え、栄養面からのアドバイスも行い、日常的にむし歯予防をサポートしています。
小児歯科のポイント④:トラブル・マタニティ歯科にも対応
転倒による歯の怪我やマタニティ期の治療にも対応しています。妊娠中の方には無理のない体勢や薬の使用に配慮し、必要に応じて産婦人科とも連携しています。
恵比寿で小児歯科をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。親子で通いやすい歯医者として、お子さんの健やかな歯の成長をサポートいたします。初診や検診のご予約も随時承っております。
恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科について詳しくはこちら
まとめ
子どもの歯の健康を守るには、小児歯科への定期的な通院が欠かせません。乳歯が生え始める1歳前後から3〜4か月に1回の検診を続けることで、むし歯の早期発見・予防だけでなく、歯並びやあごの成長も適切に見守ることが期待できます。
お子さんの歯の健康を長く守るためにも、気になることがあれば早めに相談し、定期検診を継続していきましょう。小児歯科の通院頻度や検診内容についてお悩みの方は、恵比寿の歯医者「恵比寿I’s歯科・矯正歯科」までお問い合わせください。
子どもが虫歯になりやすい理由とは?見直すべき生活習慣とケア方法
2025年10月22日
▼目次
子どもの歯は大人の歯に比べてやわらかく、虫歯になりやすい特徴があります。また、痛みをうまく伝えられないことで、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。「毎日歯磨きをしているのに、なぜ虫歯になるの?」と感じている親御さんも多いのではないでしょうか。今回は、子どもが虫歯になりやすい理由と、見直すべき生活習慣やケアのポイントについて解説します。
1. 子どもが虫歯になりやすいのはなぜ?
子どもの歯は構造的にも生活習慣的にも、虫歯が発生しやすい環境にあります。まずは、その主な原因を理解しておくことが大切です。
①乳歯のエナメル質の弱さ
乳歯は大人の歯よりもエナメル質(歯の表面を覆う硬い層)が薄く、酸に溶けやすいという特徴があります。そのため、虫歯菌が出す酸に対して抵抗力が弱く、短期間で進行してしまう傾向があります。
②食べかすが残りやすい構造
子どもの歯は小さく、歯と歯の間が詰まっているため、食べかすが残りやすくなります。特に奥歯の溝には汚れが溜まりやすく、歯ブラシが届きにくいため、磨き残しが虫歯の原因になる場合もあります。
➂仕上げ磨きが十分でない
幼児期の子どもは自分で正しく歯を磨くことが難しく、保護者の仕上げ磨きが欠かせません。仕上げ磨きを省略したり、十分に行わないと、汚れが残って虫歯リスクが高まる可能性があります。
④保護者からの虫歯菌感染
スプーンの共有や口移しなどで、虫歯菌が親から子へ感染することがあると言われていました。最近では、虫歯は感染するものではなく、口腔内の最近のバランスの不均衡により、小実ものと言われています。とは言え、特に1歳半〜3歳ごろは、虫歯菌が定着しやすい時期といわれています。保護者の方の口腔内も清潔な状態にすることが子どもの虫歯を予防する第一歩になると言えます。
毎日の歯磨きや生活習慣の工夫が、虫歯予防につながるでしょう。
2. 食事やおやつのタイミングが虫歯に影響する理由
食事内容だけでなく、食事の時間や間隔も虫歯の発生に関係するといわれています。虫歯菌は糖分を分解して酸を出し、歯を溶かすことがあるため、口腔内が酸性に傾く時間を短くすることが大切です。
①だらだら食べが続くと口腔内が酸性になりやすい
食事やおやつを頻繁に摂ると、唾液が中和する時間が少なくなり、口腔内が酸性状態のままになりやすくなります。その結果、エナメル質が溶けやすくなり、虫歯ができることがあります。
➁糖分の摂取頻度が高いと菌が活発化しやすい
虫歯菌は、糖を栄養源として増えるといわれています。甘いお菓子やジュースを一日に何度も摂ると、菌の活動が活発になり、歯を溶かす酸が長時間作られる可能性があります。
③夜間の飲食は虫歯リスクが高まりやすい
睡眠中は唾液が減るため、寝る前におやつやジュースを摂ると、口腔内が酸性状態のままになりやすくなります。特に乳歯は溝や隙間が多いため、食べかすが残りやすく、虫歯につながることがあります。
④食後の口腔ケアで酸の影響を抑えられることもある
食後はできるだけ早めに歯を磨くか、難しい場合はうがいをして食べかすを洗い流すことが大切です。唾液を増やすために、しっかり噛む習慣をつけるのも効果的です。
食事やおやつのタイミングを工夫することで、虫歯のリスクを大幅に減らすことが期待できます。子どもの食習慣を見直し、歯を守るリズムを整えるようにしましょう。
3. 子どもの虫歯を防ぐケア方法
子どもの歯を虫歯から守るには、家庭での毎日のケアが欠かせません。歯磨きだけでなく、食習慣や生活リズムを整えることも大切です。
①仕上げ磨きを丁寧に行う
子どもは自分で上手に磨くことが難しいため、小学校中学年ごろまでは保護者の仕上げ磨きが必要です。奥歯や歯の間、歯ぐきの境目を中心にしっかり磨きましょう。
➁フロスやフッ素入り歯磨き粉を活用する
歯ブラシだけでは落としきれない歯の間の汚れは、フロスを使って除去しましょう。さらに、フッ素入り歯磨き粉を併用することで、歯の再石灰化を助け、虫歯菌の活動を抑える効果が期待できます。
➂おやつとジュースの時間を決める
甘いお菓子やジュースをだらだら摂ると、口腔内が酸性に傾き、虫歯が進行しやすくなります。おやつの時間を決め、水やお茶を基本にしましょう。
④よく噛んで唾液を増やす
唾液は口腔内の酸を中和したり、虫歯菌の働きを和らげることもあります。食事ではよく噛む習慣をつけるとよいでしょう。
⑤寝る前の飲食を控える
就寝中は唾液が減るため、虫歯が進行しやすくなります。寝る前は飲食を避け、歯磨きを済ませてから寝ることが大切です。
毎日の少しの工夫と習慣の積み重ねが、子どもの歯を虫歯から守る大きな力になるでしょう。
4. 恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科

恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科では、小児歯科において「怖い」「痛い」といった従来の歯医者のイメージを変えるための取り組みを行っています。お子さんが安心して通えるよう、治療前の雰囲気づくりや歯列矯正の早期対応、むし歯予防の栄養指導、さらには急な歯のトラブルやマタニティ歯科まで幅広く対応し、親子で通える歯医者を目指しています。
【恵比寿の歯医者 恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科の特徴】
小児歯科のポイント①:歯医者に慣れる工夫
初めて来院するお子さんには治療を急がず、雰囲気に慣れる時間を大切にしています。スタッフとの会話やごほうびを通じて「歯医者は怖くない場所」という印象を持っていただけるよう心がけています。
小児歯科のポイント②:早期の歯列矯正に対応
子どもの歯列矯正は早めに始めることで、治療期間や費用を抑えることにつながります。当院では矯正歯科も併設しており、成長に合わせたご提案が可能です。
小児歯科のポイント③:予防のための栄養指導
虫歯は生活習慣や食生活とも密接に関係しています。歯磨き指導に加え、栄養面からのアドバイスも行い、日常的にむし歯予防をサポートしています。
小児歯科のポイント④:トラブル・マタニティ歯科にも対応
転倒による歯の怪我やマタニティ期の治療にも対応しています。妊娠中の方には無理のない体勢や薬の使用に配慮し、必要に応じて産婦人科とも連携しています。
恵比寿で小児歯科をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。親子で通いやすい歯医者として、お子さんの健やかな歯の成長をサポートいたします。初診や検診のご予約も随時承っております。
恵比寿I’s歯科・矯正歯科の小児歯科について詳しくはこちら
まとめ
子どもの歯は大人の歯より弱く、生活習慣や磨き残しによって虫歯になりやすい特徴があります。
毎日の仕上げ磨きやフロスの使用、フッ素入り歯磨き粉の活用を続けることで、虫歯のリスクを減らしやすくなります。
また、食事やおやつの時間を整え、寝る前の飲食を控えることも大切です。
家庭でのケアと歯医者での定期的なチェックを組み合わせることで、子どもの歯を長く健康に保ちやすくなります。
子どもの虫歯にお悩みの方は、恵比寿の歯医者「恵比寿I’s歯科・矯正歯科」までお問い合わせください。
乳歯の歯並びが悪い場合の永久歯への影響は?治すべき?対処法を解説
2025年3月18日
▼目次
子どもの乳歯はやがて永久歯に生え変わるため、「歯並びが悪くても問題ない」と思われがちですが、乳歯の歯並びが悪いと永久歯にも影響を及ぼすことがあります。
では、乳歯の歯並びが悪くなる原因とは何でしょうか? また、将来的にきれいな歯並びを保つためにはどのような対策が必要なのでしょうか?
今回は、乳歯の歯並びが悪くなる原因や、永久歯への影響、適切な対処法について詳しく解説します。
1. 乳歯の歯並びが悪い原因とは
こどもの歯並びは、口腔内環境や生活習慣が影響を与えることもあるため、親御さんが注意を払うことが重要です。
以下に、乳歯の歯並びが悪くなる主な原因を解説します。
①遺伝的要因
親の歯並びや顎の大きさが子どもに影響を与えることがあります。
特に、顎が小さい場合は歯が生えるスペースが不足し、歯並びが悪くなる可能性が高くなります。
②指しゃぶりや舌の癖
長期間の指しゃぶりや舌を前に押し出す癖(舌突出癖)は、前歯を押し出してしまい、歯並びに影響を及ぼすことがあります。
③口呼吸
口呼吸の習慣があると、舌の位置が下がりやすくなり、正しい歯並びの発育を妨げることがあります。
④乳歯のむし歯
乳歯がむし歯になり、早期に抜けてしまうと、周囲の歯が動いてしまい、歯並びが乱れることがあります。
⑤食生活の影響
柔らかい食べ物ばかり食べていると、顎の発達が不十分になり、歯が正しく並ぶスペースが確保できなくなることがあります。
乳歯の歯並びを守るためには、これらの原因をできるだけ取り除く必要があります。
特に、日常的な癖や食習慣には早めに対策を取ることが重要です。
2. 乳歯の歯並びの悪さは治すべき?永久歯に与える影響
「乳歯はいずれ抜けるから、歯並びが悪くても問題ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、乳歯の時点で歯並びに問題があると、永久歯や将来の噛み合わせにも影響を及ぼすことがあります。
以下に、具体的な影響を解説します。
①永久歯の歯並びが悪くなる可能性がある
乳歯の歯並びが乱れていると、永久歯が正しい位置に生えるスペースが不足し、ガタガタの歯並びになりやすくなります。
特に、乳歯の早期喪失や位置異常は、永久歯の生え方に大きく影響することがあります。
②噛み合わせの異常を引き起こす
歯並びが悪いと、上下の歯のかみ合わせがズレやすくなります。
これにより、顎の成長バランスが崩れたり、将来的に顎関節症などのリスクが高まることがあります。
このように乳歯の歯並びが悪いと、永久歯にもさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。
子どもの歯並びが気になる場合は、早めに歯科医師に相談し、適切な対応を検討することが大切です。
3. 乳歯の歯並びの理想的な状態とは?
実際に子どもの歯や顎はどのような状態が理想的なのか紹介します。
お子さんの歯並びを確認する際の参考にしてみてください。
①歯の配列と咬合
☑歯が適切に並んでおり、叢生(歯の重なり)がない
☑下の歯が適切にかみ合い、反対咬合(受け口)や開咬がない
☑正常な咬合関係(例えば、上顎の前歯が下顎の前歯をわずかに覆う)がある
最近では深い噛み合わせのお子さんが多いと言われています。
②歯列のスペースと発育
☑歯と歯の間に適度な空隙(発育空隙、霊長空隙)がある
☑歯列弓が左右対称で、顎の発育が正常に進んでいる
歯と歯の間に適度な空隙があることは永久歯が生えてくるスペースを確保するために重要です。しかし最近は隙間のない歯並びのお子さんが多いです
また、口呼吸や姿勢や習癖によって歯列弓がVの字や左右非対称になる場合があります
③顎の成長と機能
☑咀嚼機能が正常で、食事時にしっかりと噛める
☑舌や口唇の動きが適切で、口腔習癖(指しゃぶり、舌突出癖など)がない
☑顎関節の動きがスムーズで、痛みや異常音がない
④歯の健康状態
☑虫歯(う蝕)がなく、歯の形態やエナメル質に異常がない
☑歯肉が健康で、炎症や出血がない
☑適切に歯磨きができており、プラーク(汚れの塊、細菌の塊)がない
4. 永久歯の歯並びを整えるために出来る対処法

乳歯の歯並びが悪い場合でも、適切な対処をすることで、永久歯の歯並びを整えることが期待できます。
対処法について以下に詳しく解説します。
①生活習慣の改善
日常の習慣は歯並びに影響を与えるため、悪い癖は早めに改善することが大切です。例えば、3歳を過ぎても指しゃぶりが続く場合は、歯科医師の指導を受けながらやめるようにしましょう。また、口呼吸は歯並びの乱れにつながることがあり、アレルギー性鼻炎や扁桃腺の肥大が原因となることもあるため、必要に応じて耳鼻咽頭科、小児科を受診することも検討しましょう。
②食生活の見直し
噛む力が弱いと顎の発達が不十分になり、歯並びが悪くなる原因になります。そのため、根菜類やナッツ類などの硬めの食材を積極的に取り入れ、しっかり噛む習慣をつけることが大切です。食事の際に意識してよく噛むことで、顎の成長を促し、歯並びの乱れを防ぐことにつながります。
③定期検診を受ける
歯並びのチェックやむし歯の早期発見のために、3〜6か月ごとに定期的な歯科検診を受けることが大切です。歯科医師による噛み合わせの確認を受けることで、乳歯の段階で異常が見つかった場合も、早期に適切な治療ができる可能性があります。
④必要に応じて小児矯正を検討する
歯並びや噛み合わせの問題が大きい場合は、矯正治療を検討するのも一つの方法です。例えば、痛みが少なく取り外し可能なマウスピース型矯正装置を使う方法や、顎を広げて歯が並ぶスペースを確保する床矯正などの治療法があります。
5. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療
恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科では0歳から通院頂くことを推奨しております。
歯が無い状態で何を治療するの?と思われるかもしれませんが、歯並びや顔立ちは生活習慣が影響します。
0歳から通院頂くことで、むし歯の早期発見はもちろん、親子で栄養、食事、姿勢や顔貌の発育、睡眠、呼吸、咀嚼の質向上を目指しております。
《恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療の取り組み》
恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科では0歳から通院頂くことを推奨しております。
歯が無い状態で何を治療するの?と思われるかもしれませんが、歯並びや顔立ちは生活習慣が影響します。
0歳から通院頂くことで、親子で栄養、食事、姿勢や顔貌の発育、睡眠、呼吸、咀嚼の質向上を目指しております。
《恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療の取り組み》
➀子どもが歯医者の雰囲気に慣れることを大切に
スタッフとのコミュニケーションを通じてリラックスできる時間の確保や、通院が楽しくなる雰囲気づくりなどを心がけています。
➁早い段階での子どもの歯列矯正
子どもの歯列矯正を早期に行うことで、より健康的な歯並びと願望の成長ができます。さらには将来的に治療期間と費用を抑えられる可能性があります。
➂むし歯予防のための子どもの栄養指導
普段の食事と栄養バランスは歯の健康に影響を与えます。
当院では、歯磨き指導だけでなく栄養指導も行い、子どもたちの歯を守るお手伝いをします。
➃子どもの急な歯のトラブルに対応
「歯をぶつけた」「口周りのケガをした」このように迅速な診察が必要なトラブルにも対応可能です。
➄マタニティ歯科
お子さんだけでなく、妊娠中のお母さんにも産前・産後の最適な治療環境を整えています。
必要に応じて産婦人科と連携を取りながら治療方法を選択しています。
恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、お子さんに最適な治療をご提案します。渋谷区・恵比寿周辺でお子さんの口腔内に関するお悩みの方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科にご相談ください。
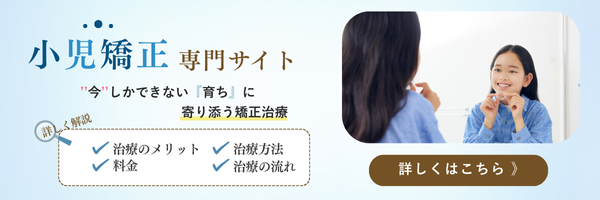
子どもの歯は何本生える?乳歯が生える時期や永久歯に与える影響を解説
2025年3月11日
▼目次
乳歯の本数や生え方を知ることは、子どもの歯を守る上で重要なポイントです。乳歯の口腔ケアを怠ると、永久歯の歯並びや将来の口の中の健康にまで影響を与えてまう事を知っていますか?
今回は、乳歯の本数や生える順番、生える時期、さらに永久歯への影響や注意点について詳しく解説します。
1. 子どもの歯は何本?乳歯の生える順番と特徴
乳歯は子どもの口の中で最初に生える歯で、永久歯が生えるまでの間、食べ物を噛んだり、言葉を発音する上で重要な役割を果たします。
乳歯のことをしっかり理解し、口の中の健康を守りましょう。
①乳歯は全部で20本ある
乳歯は上と下の歯それぞれ10本ずつ、合計20本の乳歯が生えます。
人によって最初から歯の本数が少なかったり、2本の歯がくっついて生えてきたりする場合もあります。
②乳歯が生える順番
乳歯は前歯(乳切歯)、前歯の隣(乳側切歯)、奥から2番目(第一乳臼歯)、犬歯(乳側切歯の隣)、1番奥(第二乳臼歯)の順で生え、食事や発音に必要な役割を果たします。
・生後6か月頃から:下の前歯(乳切歯)
・生後10ヶ月頃:上の前歯(乳切歯)
・1歳頃:上の前歯の隣(乳側切歯)
・1歳4ヶ月頃:第一乳臼歯(奥から2番目)
・1歳7ヶ月頃:乳犬歯
・2歳半頃:乳小臼歯(1番奥歯)
個人差はありますが、平均して2歳半〜3歳で乳歯が生え揃うことが多いでしょう。
③乳歯は永久歯よりむし歯になりやすい
乳歯は永久歯と比べて、歯の質が弱くむし歯になりやすい特徴があります。
また歯が小さくの厚みも薄いため、むし歯ができると進行が早いので注意が必要です。
乳歯が生える順番や時期は、個人差が大きく必ずしもその通りに生えてくるとは限りません。
多少のズレは気にしなくても大丈夫な場合もありますが、心配な場合は歯科医院で相談しましょう。
2. 子どもの歯が生える時期と口腔ケア
乳歯が生える時期は、子どもの成長の目安にもなります。それぞれの時期に対応するケアを行いましょう。
①0歳〜生後6か月までの歯が生えてない時期
乳歯が生えるまでの間、歯ブラシをする必要はありません。しかし、食後に水に濡らして絞ったガーゼで口の中を拭くことで歯ブラシを始めた時の抵抗が少なくなりやすいでしょう。
②生後6か月頃から乳歯が生えてくる時期
下の前歯(乳切歯)が最初に生えるのが一般的です。
歯が生えてきたら、歯ブラシで磨きましょう。乳歯用の小さいヘッドのものを選んで少しずつ歯ブラシを慣れさせていくことが大切です。
③3歳頃までに乳歯が生え揃う時期
平均して3歳頃までに乳歯20本が生え揃うことが多いです。
歯ブラシに慣れて隣り合う歯が何本か生えてきたら、歯ブラシと合わせてデンタルフロスも使うようにしましょう。
子どもの口の中は小さいので、ホルダー付きのフロスだと操作しやすくなります。
④6歳頃からの永久歯への交換時期
6歳頃から乳歯が抜け始め、永久歯に入れ替わります。この時期は永久歯の歯並びの基礎が形成される重要な時期です。乳歯がむし歯が進行すると、永久歯の形や色に影響がある場合もあります。
歯ブラシを嫌がる子どもに対しては無理せず、口の周りを触る練習や、歯ブラシに慣れさせるところから徐々に始めるといいでしょう。子どもだけでは歯を磨くのは難しいので、必ず仕上げ磨きをする事が大切です。
3. 子どもの歯が生え揃わない時
乳歯が予定通りに生え揃わない場合や順番が乱れる場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?考えられる主な原因は以下の通りです。
①個人差による生えるペースの違い
1歳を過ぎても歯が生えない場合、遺伝的な要因や栄養状態の影響が考えられます。
しかし乳歯生える時期や順番にはかなり個人差があります。多少のズレは問題ありませんが、心配な場合は歯科医院で相談しましょう。
②生まれつき歯がない(先天性欠如)
出てくるはずの乳歯がそもそもない先天性欠如という場合もあります。あまりにも生えてこない場合、レントゲンで歯肉の中に歯があるかを確認する必要があるでしょう。
③歯と歯がくっついている(癒着歯)
1本で生える予定の歯が複数の歯がくっついていることにより生える時期が遅れる場合もあります。
これは癒合歯と呼ばれるもので、通常様子を見ながら、永久歯に生え変わるのを待つことが多いです。
乳歯がなかなか生え揃わないと心配になることも多いですが、遺伝的な要因や個人差も大きく関わっています。定期的に歯科医院にいくことで問題を早期に発見する事が期待できます。
4. 乳歯が永久歯に与える影響

乳歯の状態が悪いと、永久歯の健康や歯並びに影響を及ぼします。
そのため、乳歯のケアは将来の歯の健康を考える上でとても大切です。
乳歯が永久歯に与える影響は以下の通りです。
①永久歯の歯並びに影響を与える
乳歯が正しい位置で抜けない場合、永久歯の生えるスペースが不足し、歯並びが乱れることがあります。
②乳歯から永久歯にむし歯が移ることがある
いつか抜けるからと乳歯のむし歯を放置していると、永久歯にもむし歯菌が移り、生えてきたと同時にむし歯ができている場合もあります。
③噛み合わせに問題が出やすい。
むし歯により乳歯が早くに抜けてしまったり、乳歯が生えているのに永久歯が生えてきてしまった場合、歯並びが乱れやすく、永久歯の噛み合わせに悪影響を及ぼす場合があります。
恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、お子さんに最適な治療をご提案します。渋谷区・恵比寿周辺でお子さんの口腔内に関するお悩みの方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科にご相談ください。
乳歯に行うシーラントとは?効果やメリット・注意点を解説
2025年2月17日
▼目次
子どもの歯である乳歯は、永久歯に比べて歯の表面のエナメル質が薄く、むし歯になりやすい特徴があります。
特に奥歯の溝やくぼみは食べ物が詰まりやすく、歯ブラシが届きにくいため、むし歯リスクが高い部分です。
そんな乳歯のむし歯予防として注目されているのが「シーラント」です。
今回は、シーラントの基本情報や効果、乳歯にシーラントを施すタイミング、さらにそのメリットとデメリットについて解説します
1. シーラントとは?効果やメリットを解説
シーラントとは、歯の溝やくぼみに特殊な樹脂を塗布して固める処置で、以下のような効果があります。
➀むし歯の予防
歯の溝を埋めることで、むし歯菌の侵入や繁殖を防ぎます。特に歯磨きが不十分な年齢の子どもに効果的です。
➁高い予防効果
処置後すぐに効果を発揮し、特に乳歯や生えたての永久歯に対して適用することで、高い予防効果が得られる可能性があります。
➂むし歯の進行抑制
初期段階のむし歯が見られる場合でも、シーラントを施すことで進行を抑えることができる場合があります。
子どものむし歯予防におけるシーラントのメリットを以下に解説します。
➀痛みがほとんどない処置
シーラントは歯を削らずに行えるため、痛みを感じることがほとんどありません。
➁短時間で終了する
シーラントは簡単な処置のため、数分から十数分で終了します。
➂口腔内の健康向上につながる
むし歯リスクを抑えられるため、歯の長期的な健康維持にも効果的です。
2.乳歯にシーラントをする適切なタイミング
シーラントは、乳歯がむし歯になるリスクが高いタイミングで行うのが効果的です。
目安となる具体的なタイミングを以下に解説します。
➀乳歯が生え揃った頃
乳歯の奥歯は溝が複雑な形をしており、深くなっています。
乳歯が生え揃う時期は奥歯の溝がむし歯菌の温床になりやすいため、予防効果が高いとされています。
➁むし歯の初期兆候が見られた場合
歯の表面が白っぽく濁っていたり、歯の表面がザラザラしていたりする場合は、むし歯の初期段階である可能性があります。
このタイミングでシーラントを施すことで、むし歯の進行を防ぐことが期待できます。
➂定期検診で指摘された場合
定期検診時に歯科医師からシーラントの必要性を指摘された場合は、早めに対処するのが良いでしょう。
シーラントを適切なタイミングで行うことで、むし歯のリスクを効果的に抑えられます。
3. 乳歯にシーラントをする際の注意点
シーラントは効果的なむし歯予防策ですが、以下の点に注意が必要です。
➀施術後の定期的なメンテナンス
シーラントの効果は、一般的に3~5年ほど持続するとされていますが、食べ物の硬さや歯の使い方によっては早めに摩耗してしまうことがあります。
そのため、定期的に歯科医師のチェックを受けることが大切です。
➁歯磨きの習慣を怠らない
シーラントは歯の溝を保護しますが、全ての歯面をカバーするわけではありません。
日常の丁寧な歯磨きやフロスを用いたケアが必要です。
➂むし歯予防は包括的に
シーラントだけではむし歯を完全に防ぐことはできません。
バランスの良い食事や歯科医院でのフッ素塗布など、総合的な予防策を取り入れることが推奨されます。
定期検診を受診したり、日頃からこまめなケアを取り入れたりすることで、さらにむし歯の予防効果を高めることが期待できます。
シーラントは、乳歯をむし歯から守るための効果的な処置で、特に奥歯の溝の深い部分に対して、簡単かつ痛みの少ない方法でむし歯予防が期待できます。
しかし、処置を行うタイミングやシーラントの特性を理解することが大切です。
また、日々の歯磨きや定期検診と組み合わせることで、シーラントの効果を長持ちさせる可能性が高まります。
4. 恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科では0歳から通院頂くことを推奨しております。
歯が無い状態で何を治療するの?と思われるかもしれませんが、歯並びや顔立ちは生活習慣が影響します。
0歳から通院頂くことで、むし歯の早期発見はもちろん、親子で栄養、食事、姿勢や顔貌の発育、睡眠、呼吸、咀嚼の質向上を目指しております。
《恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療の取り組み》
➀子どもが歯医者の雰囲気に慣れることを大切に
スタッフとのコミュニケーションを通じてリラックスできる時間の確保や、楽しいイベントや「頑張ったごほうび」で通院が楽しくなる雰囲気づくりなどを心がけています。
➁早い段階での子どもの歯列矯正
子どもの歯列矯正を早期に行うことで、より健康的な歯並びと願望の成長ができます。さらには将来的に治療期間と費用を抑えられる可能性があります。
➂むし歯予防のための子どもの栄養指導
普段の食事と栄養バランスは歯の健康に影響を与えます。
当院では、歯磨き指導だけでなく栄養指導も行い、子どもたちの歯を守るお手伝いをします。
➃子どもの急な歯のトラブルに対応
「歯をぶつけた」「口周りのケガをした」このように迅速な診察が必要なトラブルにも対応可能です。
➄マタニティ歯科
お子さんだけでなく、妊娠中のお母さんにも産前・産後の最適な治療環境を整えています。
必要に応じて産婦人科と連携を取りながら治療方法を選択しています。
恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、お子さんに最適な治療をご提案します。渋谷区・恵比寿周辺でお子さんの口腔内に関するお悩みの方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科にご相談ください。
子どものキシリトール摂取はむし歯予防になる?その理由や適量について解説
2025年2月14日
▼目次
子どものむし歯を予防する方法の一つとして、キシリトールの摂取が挙げられます。お菓子やガムに含まれる甘味料として知られているキシリトールですが、具体的にどのような効果があるのでしょうか?
また、子どもに与える際の適切なタイミングや注意点を知っておくことは、親御さんにとって非常に重要です。
今回は、キシリトールの特徴やむし歯予防効果、適切な摂取量について解説します。
1. キシリトールが子どものむし歯が予防になる理由
キシリトールとは、糖アルコールとよばれる天然由来の甘味料のひとつです。
キシリトールがむし歯予防に役立つ理由を以下に解説します。
➀ミュータンス菌の抑制作用
キシリトールはむし歯の原因となるミュータンス菌の活動を弱める効果があります。
具体的には、キシリトールはミュータンス菌が糖を代謝する過程を妨げて、酸の生成を抑制する事で歯のエナメル質の溶け出しを防ぐ効果があります。
➁再石灰化の促進
酸で溶け出してしまった歯の表面を修復する「再石灰化」を促すとされています。
➂唾液の分泌を促す
キシリトールはガムや飴に含まれることが多いため、唾液が多く分泌されます。
唾液には抗菌作用があるため、口腔内環境の改善が期待できます。
このような理由からキシリトールはむし歯予防に効果的といわれています。
しかし、キシリトール単体ではなく、他の糖アルコール(例えばソルビトールやマンニトールなど)と混合される場合もあるため、成分表示を確認することが重要です。
2. 子どもはいつからキシリトールを摂取できる?年齢別の目安と注意点
キシリトールを摂取する際には、子どもの発達段階に応じた注意が必要です。
キシリトール摂取の開始時期の目安について、年齢別に解説します。
➀2~3歳頃
この時期は、むし歯予防の基礎が形成される重要な時期です。ガムではなく、タブレットなどの形状が適しています。この時期は噛む力がまだ十分でないため、飲み込みやすい形状を選ぶことが大切です。必ず保護者が見ているところであげるようにして下さい。
➁4~6歳頃
噛む力が十分に発達するため、キシリトールガムを取り入れることが可能になります。
ただし、誤って飲み込んでしまう危険があるため、十分に注意しましょう。
➂小学生以降
自己管理ができるようになり、ガムや飴をむし歯予防の一環として取り入れて問題ないでしょう。
キシリトールを摂取する際は、以下の点に注意しましょう。
・初めて与える際はアレルギー反応が出ないか確認してください。
・砂糖や他の添加物が含まれているとむし歯リスクが高くなる可能性があるため、純粋なキシリトール製品を選ぶようと良いでしょう。
3. 子どもに与えるキシリトールの適量と選び方のコツ
キシリトールは適量を守って摂取することで、むし歯予防が期待できます。
しかし、過剰摂取は消化不良を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
子どもに与えるキシリトールの適量と、キシリトール製品の選び方について、以下に解説します。
<キシリトールの適量>
➀推奨摂取量
1日に5g程度がむし歯予防に効果的とされています。これを複数回に分けて摂取するのが理想的です。
➁1回あたりの目安
ガムやタブレットの場合、1回1~2個が目安です。
➂摂取回数
1日3回程度、食後やおやつの後に使用することでミュータンス菌の活動を抑える効果が高まります。
<キシリトール製品の選び方>
➀キシリトールの配合割合むし歯予防の効果を得るには
100%キシリトールも虫歯予防効果が最も高く歯に優しいですが、特定のブランドや専門店でしか見かけないこともあります。
50%以上の配合量が推奨されます。
➁砂糖不使用のものを選ぶ
キシリトールと一緒に砂糖が含まれると、むし歯予防効果が半減する可能性があります。
➂味や形状
子どもが好む味や、誤飲のリスクが低い形状の製品を選びましょう。
4.恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療

恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科では0歳から通院頂くことを推奨しております。
歯が無い状態で何を治療するの?と思われるかもしれませんが、歯並びや顔立ちは生活習慣が影響します。
0歳から通院頂くことで、むし歯の早期発見はもちろん、親子で栄養、食事、姿勢や顔貌の発育、睡眠、呼吸、咀嚼の質向上を目指しております。
《恵比寿歯科・矯正歯科の小児歯科診療の取り組み》
➀子どもが歯医者の雰囲気に慣れることを大切に
スタッフとのコミュニケーションを通じてリラックスできる時間を確保したり、楽しいイベントや「頑張ったごほうび」で通院が楽しくなる雰囲気づくりを心がけています。
➁早い段階での子どもの歯列矯正
子どもの歯列矯正を早期に行うことで、将来的に治療期間と費用を抑えられる可能性があります。
➂むし歯予防のための子どもの栄養指導
普段の食事と栄養バランスは歯の健康に影響を与えます。
当院では、歯磨き指導だけでなく栄養指導も行い、子どもたちの歯を守るお手伝いをします。
キシリトールは、子どものむし歯予防に効果的です。ただし、適切な量やタイミング、お子さんに合った製品選びが重要です。特に小さいお子さんに与える際は、形状や飲み込みに注意しましょう。
➃子どもの急な歯のトラブルに対応
「歯をぶつけた」「口周りのケガをした」このように迅速な診察が必要なトラブルにも対応可能です。
➄マタニティ歯科
お子さんだけでなく、妊娠中のお母さんにも産前・産後の最適な治療環境を整えています。
必要に応じて産婦人科と連携を取りながら治療方法を選択しています。
恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科では、お子さんに最適な治療をご提案します。渋谷区・恵比寿周辺でお子さんの口腔内に関するお悩みの方は、恵比寿駅2分の歯医者 恵比寿歯科・矯正歯科にご相談ください。
歯列矯正はいつから?小学生のうちに始めた方が良いケースと早期治療のメリット
2024年12月27日
▼目次
子どもの歯列矯正を考える際、「いつから始めるのが良いのか?」と悩む親御さんは多くいるのではないでしょうか。
特に子どもの場合、生え変わりの適切なタイミングで矯正治療を始めることが大切です。
今回は、小学生のうちに歯列矯正を始めた方が良いケースや、そのメリットと注意点、さらに治療にかかる期間について詳しく解説します。
1. 小学生のうちから矯正治療をした方が良い?
小学生のうちから矯正治療を始めるかどうかは、お子さんの歯並びや顎の発育状況によって異なりますが、小学生から始めた方がよい場合もあります。
以下に、その理由と早期治療のメリットについて説明します。
①顎の成長を活用できる
小学生の時期は顎の成長が活発であり、この成長を利用して顎を正しい位置に誘導できます。これにより、永久歯の生えるスペースを確保しやすくなります。
②むし歯や歯周病のリスク低減
歯が重なっていると磨き残しが生じやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まります。早期矯正で歯並びを改善することで、これらのリスクを抑えることが可能です。
➂将来の複雑な治療を回避
早い段階で矯正を始めることで、成長後に複雑で長期的な治療が必要になる可能性を減らすことに繋がります。
2. 小学生のうちから歯列矯正をした方が良い歯並びとは
歯並びが悪いと見た目だけでなく、噛み合わせや発音、将来の健康にも影響を与えることがあります。
ここでは、小学生のうちに矯正治療を検討した方が良い場合の具体的な歯並びについて解説します。
➀上下のあごのバランスが良くない
上の前歯よりも下の前歯が前に出ている受け口や、下の前歯より上の前歯が出ている出っ歯を放置すると、噛み合わせの悪さから顔全体のバランスに影響を与える可能性があります。
➁左右の噛み合わせがずれている
噛み合わせが左右にずれている状態は、左右差によりバランスが崩れ、片方のあごだけに負担がかかることで、噛みにくいだけではなく、顎関節症のリスクが高まる可能性があります。
➂歯が重なって生えている
スペースが足りず、歯が重なり合って生えているガタガタの歯並びは、磨きにくいことで歯磨きがしにくくなり、むし歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。
➃前歯が噛み合わず隙間がある
前歯の上下に噛み合わない隙間があると、発音や食べ物を噛む機能に問題を引き起こす可能性があります。
特に「サ行」や「タ行」の発音がしにくくなる場合があり、早めの治療が推奨されます。
3. 子どもの歯列矯正にかかる期間
子どもの矯正治療にかかる期間は、歯並びの状態や治療内容によって異なりますが、一般的には1年半から3年程度が目安とされています。
治療期間を左右する主な要因は以下の通りです。
➀どのくらい歯並びに問題があるか
歯の重なりが軽度であれば短期間で治療が終了する場合がありますが、大幅な歯の移動が必要な場合は、治療期間が長くなることがあります。
➁どの矯正方法で治すか
拡大床(顎を広げる装置)やヘッドギアを使用する場合は、どの装置を使うかで治療期間が変わってきます。
➂装着時間を守れるか
拡大床など取り外し式の装置を正しく装着することや、どのくらいの時間装着できるのかで、全体の矯正期間に差が出やすいです。
4. 子どものうちに歯並びを矯正するメリットと注意点
子どものうちに歯列矯正を始めることは、歯並びだけでなく全体の健康にも良い影響を与えます。
子どものうちに矯正を始めるメリットは以下の通りです。
①むし歯や歯周病の予防に繋がる
歯並びが整うと細かい部分まで歯磨きがしやすくなり、食べ物が歯に詰まりにくくなるため、むし歯や歯周病のリスクを減らすことに繋がります。将来の歯の健康を守る基盤を築けるのは大きなメリットです。
②心理的なストレス軽減の可能性
歯並びを改善することで人とコミュニケーションに積極的になれたり、笑顔に自信を持ちやすくなる可能性があります。
コンプレックス解消は自己肯定感を高めるだけではなく、気持ちも明るく前向きになるでしょう。
③成長を利用して治療が進みやすい
子どもの顎や歯は成長途中のため、大人よりも歯や顎を動かしやすい状態です。
そのため、短期間で治療を進められる場合があります。
④将来の複雑な矯正を避けられる
子どものうちにスペース不足や噛み合わせの問題を解決しておくことで、大人になってからの矯正治療が不要になる、または軽度で済むことがあります。スペースをつくることで歯を抜く必要がなくなるケースもあります。
5.子どもの矯正治療を進める上での注意点
➀お子さん本人の協力が必要
矯正治療では、毎日の装置の装着や食後の歯磨きがとても重要です。
矯正装置を適切に装着したり清掃したりしないと、治療が思うように進まない場合があります。
お子さんが装置を使いやすいよう、親御さんがサポートすることも大切です。
➁治療中の負担を理解する
矯正装置を装着し始めた頃は、違和感や軽い痛みを感じることがあります。このような場合は、無理せずお子さんに寄り添い、歯科医師に相談しながら対応しましょう。
➂長期的な治療計画を考える
子どもの成長に合わせた矯正治療は、1~3年程度で終わる場合もあれば、中学や高校まで経過観察が必要になる場合もあります。
スケジュールを確認し、家族全体で治療計画に向き合うことが大切です。
小学生のうちに歯列矯正を始めることは、顎や歯の成長を利用して効率的に治療を進められる大きなメリットがあります。
ただし、すべての子どもが早期治療を必要とするわけではないため、まずは歯科医師の診断を受けることが重要です。
お子さんの歯並びや噛み合わせに不安がある場合は、早めに歯科医院に相談し、最適な治療計画を立てることをおすすめします。
恵比寿歯科・矯正歯科では、お子さんの歯列矯正に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

赤ちゃんの歯医者デビューはいつから?早めに受診するメリット
2024年12月6日
▼目次
赤ちゃんの歯が生え始めると、むし歯や歯並びに関する心配も出てきます。早めの歯医者デビューが推奨されていますが、具体的にはいつから始めればいいのか、どのようなメリットがあるのかを気にされる方も多いでしょう。今回は、赤ちゃんが歯医者に通う適切な時期とそのメリット、受診の流れ、そして受診をスムーズに進めるためのコツについて解説します。
1. 赤ちゃんの歯医者デビューはいつから?
乳歯が生える前にも粘膜や顎や舌に気になるところがあれば生後間も無くてもご来院ください。
物心つく前から歯医者さんに通う習慣が当たり前になっている患者さんは、
デンタルIQが高く、年齢を重ねても素敵な笑顔で定期検診・メインテナンスに来院されます。
そのため歯科に対する知識や習慣から虫歯リスクが低く、治療が少ない状態で口腔内が綺麗に保つことができています。
特に口腔内に異常が見られない場合でも、3~4カ月に1回のペースで定期的に歯科医院を受診するのが理想的です。早めに口腔ケアの習慣を身につけることで、将来の歯の健康にもつながります。
2. 0歳から歯医者に通うメリット
0歳からの歯科受診には、赤ちゃんの口腔健康を守るためのさまざまなメリットがあります。
以下に、その主なメリットをご紹介します。
①むし歯予防ができる
赤ちゃんの歯医者デビューを早期に行うことで、むし歯予防に対する正しい知識が親御さんにも身につきます。むし歯リスクは乳歯が生え始めるころからあり、特に哺乳瓶でのミルクやジュースがむし歯の原因となる場合があるため、歯医者では正しい食べ物の与え方や歯磨き方法について丁寧な指導が受けられます。また、フッ素塗布などの予防処置も定期的に行うことで、リスクを減らすことができます。
②口腔内の成長を確認できる
歯の生え方や顎の成長は子どもによって異なり、成長に伴って歯並びの問題が発生する場合があります。赤ちゃんの頃から歯科医院に通うことで、歯並びや顎の異常を早期に発見できる可能性が高まります。歯科医師による定期的なチェックを受けることで、歯がきれいに並ぶためのスペースが確保されているか、また顎が正しく成長しているかを確認することができ、将来的な矯正治療の必要性も早期に把握できます。
③歯医者に慣れる
小さい頃から歯医者に通うことで、赤ちゃんは歯医者に対する恐怖心や不安を感じにくくなることが期待できます。初期の段階で歯医者に対する良いイメージを持つことができれば、定期的に通院する習慣が自然と身につき、成長してからも歯医者を避けることなく通えるようになります。
3. 赤ちゃんの歯科受診の流れ
赤ちゃんの初めての歯科受診で、どのようなことが行われるのか不安に感じる親御さんも多いでしょう。初診の流れを以下のポイントごとに解説します。
①受付と問診
初めての受診時には、保険証の提示と問診表の記入を行います。問診表には赤ちゃんの健康状態や歯磨きの習慣、食生活についての質問があり、これをもとに歯科医師が適切なアドバイスやケアを提供します。
②口腔内のチェック
歯科医師が赤ちゃんの歯の状態を確認し、歯茎や歯並びに異常がないかチェックします。この診察によって、今後の成長過程でのトラブルを未然に防ぐことができます。
③親御さんへのケア指導
歯科医師が歯磨きの方法やケア用品の選び方についてアドバイスします。さらに、食事の与え方やおやつのタイミングなどむし歯予防に役立つ知識も提供されることもあり、家庭でのケアがしやすくなるでしょう。
④予防処置(必要に応じて)
必要に応じて、フッ素塗布などの予防処置が行われることもあります。フッ素は歯のエナメル質を強化し、むし歯予防に効果的です。ただし、この処置は必須ではなく、親御さんと相談しながら進めていきます。
4. 初めての歯科受診を成功させるコツ
赤ちゃんが初めての歯科受診を楽しく、リラックスして受けられるように、親御さんができる工夫を紹介します。
①受診の時間帯を選ぶ
赤ちゃんは機嫌の良い時間帯やお昼寝のタイミングなどが決まっていることが多いです。歯科受診の予約をする際には、赤ちゃんが機嫌よく、リラックスしている時間を選ぶようにしましょう。特に朝やお昼寝の後など、体力が十分にある時間帯を選ぶことで、泣いたり不安になったりするのを防ぎやすくなります。
②お気に入りのアイテムを持参する
歯医者の待合室や診察室では、赤ちゃんが緊張したり、不安を感じたりすることがあります。そのため、お気に入りのぬいぐるみやおもちゃ、毛布などを持参すると、リラックスした状態を保ちやすくなるでしょう。
③事前に歯医者の雰囲気に慣れさせる
可能であれば、事前に歯科医院を訪れたり、診療室を見せたりすることで、場所への緊張を和らげることができます。受診前に「歯医者さんに行こうね」といった前向きな声かけをしておくことも効果的です。
④歯医者での受診をポジティブな体験にする
受診後に「よく頑張ったね!」と褒めてあげたり、ご褒美を用意したりすることで、次回も歯医者に行くのが楽しみになるでしょう。ポジティブな体験を増やすことが大切です。
⑤親御さんもリラックスする
赤ちゃんは親御さんの気持ちに敏感です。親御さんが不安な様子を見せると、赤ちゃんも緊張してしまいます。歯科医師やスタッフがしっかりとサポートしてくれるので、親御さんも安心してリラックスした状態で臨むことが大切です。
赤ちゃんの歯医者デビューは、早めに行うことでむし歯予防や口腔ケアの基礎が整い、成長に伴う口腔内の変化も確認できます。初めての受診を楽しく、安心して受けられるよう工夫することで、将来の歯科通いに対する不安を軽減し、健康な歯の土台作りが可能です。親御さんが積極的にサポートすることで、赤ちゃんの歯科習慣も自然と身につきやすくなります。
恵比寿歯科・矯正歯科では、0歳の子どもから歯の健康をサポートしています。お子さんの歯医者デビューは、恵比寿歯科・矯正歯科にお任せください。

子どもの歯磨きはいつから?小児歯科で行う口腔ケア
2024年12月3日
▼目次
子どもの歯磨きは、成長に合わせてしっかり行う必要があります。歯が生え始めたばかりの頃から、将来の健康な歯を育むためのケアが求められます。歯磨きの習慣を早いうちから身につけることは、むし歯予防だけでなく、口腔全体の健康にも繋がります。今回は、子どもの口腔ケアをいつから始めるべきか、どのように進めていくべきか、小児歯科で行われるケア方法について詳しく解説します。
1. 子どもの口腔ケアはいつから始めるべき?
子どもの口腔ケアは、口の中を清潔に保ち、歯が生える準備として口に触れることから始めます。乳児期から口に触れる経験を持たせると、歯磨きへの抵抗感が減りスムーズに口腔ケアを始められます。
一般的には、生後6か月頃になると乳歯が生え始めます。このタイミングで歯磨きをスタートしましょう。初めは柔らかいガーゼや指歯ブラシを使い、歯や歯茎を優しく清潔にすることが重要です。
2. 自宅で行う子どもの口腔ケア方法
自宅での子どもの口腔ケアは、成長段階に合わせて柔軟に取り組むことが大切です。以下の方法を参考に、子どもが歯磨き習慣を身につけやすくなる工夫をしていきましょう。
①生後6か月から1歳頃まで
この時期は、乳歯が生え始める大切な時期です。最初の歯が生えたら、柔らかいガーゼやシリコン製の指歯ブラシを使い、1日に1回優しく磨きましょう。歯ブラシを使うことが難しい場合も、唇や歯茎に触れることで子どもが歯磨きに慣れていくようサポートしていきます。
②1歳から3歳頃まで
子どもが自分で歯ブラシを持てるようになったら、柔らかい毛の歯ブラシを使って歯磨きの練習を始めます。この時期は、保護者が仕上げ磨きを行うことが重要です。フッ素入りの歯磨き粉を少量使いながら、特に前歯や奥歯の噛み合わせの部分も丁寧に磨いてあげましょう。
③3歳以上
3歳以上になると、だんだんと自分で歯を磨く習慣を身につけられるようになります。しかし、まだ磨き残しが多い可能性もあるため、保護者の仕上げ磨きは引き続き欠かせません。
3. 小児歯科で歯磨き指導を受けるメリット
小児歯科では、子どもに合った口腔ケアの方法を指導してくれます。子どもの口腔ケアがさらに効果的に行えるようになるだけでなく、将来的なトラブル予防にも繋がります。
①専門的なアドバイスが受けられる
歯科医師や歯科衛生士が、年齢や歯の成長段階に合わせた最適なケア方法を教えてくれます。どのように磨けば歯垢を効果的に除去できるか、子どもが楽しく歯磨きに取り組めるコツなど、保護者だけではわかりにくい部分も細かくアドバイスを受けられるでしょう。
②適切な予防処置を受けることができる
小児歯科では、フッ素塗布などの予防処置も行っています。特に乳歯の段階で定期的にフッ素塗布を受けることで、むし歯のリスクを軽減でき、永久歯への移行をスムーズにします。
③子どもの歯医者嫌いを防ぐ
定期的に小児歯科に通うことで、歯医者に慣れることができ、歯科医院に対する恐怖心を抱きにくくなります。初めは歯磨き指導などのケアから通院を始めると、歯科医院を「怖い場所」ではなく「口の健康を守るための場所」と認識し、将来的な治療の際にも抵抗が少なくなることも期待できるでしょう。
④早期発見・早期治療
小児歯科に定期的に通うことで、むし歯や歯並びの異常などを早期に発見できる点もメリットです。小さな異常でも早期に対処することで、大がかりな治療を避けることができ、子どもの負担を軽減できます。また、歯並びに関しても専門的なアドバイスが受けられるため、矯正が必要な場合の移行もスムーズです。
4. 子どもの仕上げ磨きのポイント
仕上げ磨きは、子どもの歯をしっかりと清潔に保つために欠かせないケアのひとつです。小さな子どもは自分で丁寧に磨くことが難しいため、仕上げ磨きを行い磨き残しを防ぐことが重要です。以下のポイントを押さえ、効果的な仕上げ磨きを行いましょう。
①柔らかい歯ブラシを使用する
仕上げ磨きでは、子どものデリケートな歯と歯茎を傷つけないように、柔らかい毛の歯ブラシを選びましょう。子ども用の小さなヘッドの歯ブラシを使うことで、口の中で操作しやすくなり、奥歯までしっかりと届きます。また、歯磨きが楽しくなるように、キャラクターがデザインされた歯ブラシなど、子どもが好むものを用意するのもおすすめです。
②歯と歯茎の境目を意識して磨く
歯と歯茎の境目は、特に汚れがたまりやすい部分です。歯ブラシの毛先が歯と歯茎の境目にきちんと当たるよう、少し傾けて優しく磨きましょう。力を入れすぎると歯茎を傷つける可能性があるため、やさしい力で小刻みに動かすのがポイントです。
③噛み合わせ部分や奥歯も忘れずに
噛み合わせ部分や奥歯の磨き残しがあると、むし歯のリスクが高まります。特に奥歯は見えにくく磨きづらい場所なので、子どもが上を向いた状態で磨くと良いでしょう。また、鏡を使いながら仕上げ磨きを行うと、磨き残しを確認しやすくなります。
④短時間で楽しく
仕上げ磨きは、子どもにとって「楽しい時間」と感じられるように工夫すると、歯磨き習慣が身につきやすくなります。好きな音楽をかけたり、歌を歌いながら磨いたりして、歯磨きをポジティブな体験にするようにしましょう。また、時間が長すぎると子どもが嫌がることがあるため、短時間で終わらせるよう心がけます。
⑤毎日の習慣として定着させる
仕上げ磨きは毎日の習慣にすることが大切です。特に夜寝る前の歯磨きはむし歯予防に重要です。就寝前に家族で一緒に歯磨きタイムを設けるなど、日常の習慣として定着させていきましょう。
子どもの口腔ケアは、乳歯が生え始める前から考えることが大切です。家庭での口腔ケアと小児歯科での指導を組み合わせ、正しい歯磨き方法やむし歯予防を学ぶことで、子どもの歯の健康を守ることができます。
恵比寿歯科・矯正歯科では、専門的な知識と豊富な経験を活かし、0歳の子どもから歯の健康をサポートしています。
むし歯の治療や予防に関するご相談は、お気軽にお問合せください。